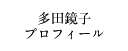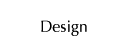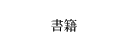- 01 The Boomers
- 02 あの頃
- 03 Chicken Dog
- 04 Ellen David
- 05 Drum Solo
- 06 Nefertiti
- 07 Last Year
- 08 Y
- 09 Someday My Prince Will Come
STLR-011
¥3,000+税
発売元:株式会社ラルゴ音楽企画
※全国レコード店、またはスタジオ・トライブ店頭でも販売しています。
藝大卒業と『Boys featuring SHUN』の発売とこれからの活動のこと
石若駿 インタビュー
- これからの音楽活動は、在学中と変わるでしょうか?
- 藝高に入学してから現在までの7年間は、クラシックの打楽器を一からしっかり学びました。カルテットをはじめとする色々な編成の打楽器アンサンブル、オーケストラ、そしてコンチェルトまで、毎日のように練習を積み、難曲にも挑戦しました。幸運にも、願ってもない多くの演奏機会を持てたと思います。
学業の傍ら、ジャズのライブにも恵まれて、授業や練習が終わるとシンバルを背負って街に出かけ、ライブハウスで演奏するというサイクルでした。間もなく卒業を迎えますが、それ以後は学業に当てていた時間が自由に使えるので、自分の音楽を創り上げるのに充てられればと考えています。
- すでにレコーディングするなど、手がけている自分の音楽とは、具体的にどのようなものなのでしょう?
- ジャズのユニットで演奏するもの以外に、高校生の頃から作曲してきた作品に、詞をつけて貰い歌ってもらう、というプロジェクトを始めています。色々な人に参加をオファーしていますが、打楽器、ドラム、鍵盤などを自分で演奏しながら下地を作っています。これからそこに、ベースや弦楽器などを取り入れていく予定です。
- 作曲や編曲をこれからの活動の主体にと考えているのでしょうか?
- どれを主体にと、限定的に考えることはしていません。
この春は、卒業を待ってくれていたたくさんの方たちと、ライブハウスの共演が目白押しです。しかし、自分には他にやれることがたくさんあるはずなので、どの部分も無駄にしない活動の仕方にチャレンジしなくてはと思っています。もしかすると、今まで誰もやっていない、自分にしかできない活動があるのでは、と思ったりします。
- たしかに、クラシック音楽の最高学府で学び、しかも数多くのジャズミュージシャンとの共演の履歴を見ると、ユニークな存在だということは明らかですね。
- 自分でもそう思い続けていたいです。
例えば、この春にルクセンブルクで打楽器のカルテットのコンペティションに参加しました。惜しくもセミ・ファイナルで敗退しましたが、世界中から参加した同年代の演奏家たちを間近で聴き、交流できたことはまたとない刺激になりました。
昨年秋には、藝大のモーニングコンサートで、オーケストラをバックに打楽器コンチェルトを演奏させて頂くという、稀な機会にも恵まれました。藝祭では、同窓の大先輩ドラマーの森山威男さんとツイン・ドラムで演奏し、収録もしました。これらの経験は本当に貴重だと思っています。
- 軸足は、ややクラシックに寄り気味でしょうか?
- そうとも言えなくて、バックグラウンドにジャズがある打楽器奏者、そしてドラマーでもある、というところでしょうか。
近年は、現代音楽の新作で、ビート・ミュージックに対応できる打楽器奏者として採用したい、というオファーが少なからず来ます。なかなかブッキングにまでは至りませんが、ここも独自の活動分野であることは自覚しています。これまではブッキングにあまり神経を使っていませんでしたが、できれば、指名を頂くような機会は、これから漏らさず実現していかなくては、と思うようになりました。 - ブッキングに工夫が要りますね。
- そう思います。だから自分の考えを、もっと声に出して言わなくてはなりません。これからは学業がなくなる分、日々、何を主体にして活動を組み立てていくかが重要課題です。自分が大きな音楽の世界の中で、どのような存在になるのか。それを決めるのは自分の責任でしょう。だから、特定のタスクの専門家です、ということではなく、どんなことを頼まれても、自分の知識や技術や発想で、そのオファーをどう発展させ展開するべきか。最初のアイディア時点から考え始めるようにしたいですね。作曲、編曲、演奏、そして最近始めたレビューなどの執筆活動も含め、今、自分のできることを懸命に続けながら新しく発展させ、視野を広げていきたいのです。
だから、勇気を持って「誰でも無い、ただ一人の石若駿になる」と言ってみたいです。 - 自分の可能性を狭めないで、新しい活動スタイルを模索する、という感じでしょうか。今、楽しみにしていることはありますか?
- 100人でミニマル・ミュージックを演奏する東京塩麹、挑戦的なジャズをやる東京ザヴィヌルバッハ、Boys Trioやアーロン・チューライとの活動、他ゲストで呼ばれる沢山のバンドがあります。どれもかけがえが無く、必ず何かを掴めるし、掴むものを自分で探しています。
そして、今すごく楽しいのは、同世代の若いミュージシャンとの連携です。現在の音楽シーンに対して感じることを起爆剤として、挑戦し、問題提起もしていきたいと。ちょっと暴れる感じかな。同世代のみんなと一緒に、どんどん成長していくことを楽しみにしています。
- インタビュー中、「こんな風に自分の考えを話したのは初めてだ」と、嬉しそうな表情を見せたのが印象的だった。
石若駿は、22歳にして、貴重で稀な沢山の経験を積んできた。時々、先輩の目や意見も気になりながら、しかし、自分の可能性には熱い期待を抱いているように見える。確かに、これまで誰も踏み出せなかった世界へと足を踏み入れているのだ。